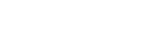本文
後期高齢者医療制度の概要
後期高齢者医療制度の概要
平成20年4月から老人保健制度に代わり、75歳以上のすべての方と一定の障がいがある65〜74歳の方を対象とした、後期高齢者医療制度が始まりました。
以下、制度の概要をご紹介します。詳しくは新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
制度の運営主体
制度の運営は、後期高齢者医療広域連合が行います。(市町村は窓口業務、保険料の収納業務を行います)
後期高齢者医療広域連合とは、後期高齢者医療を運営する都道府県単位の特別地方公共団体です(市町村等からの派遣職員等で事務を行ないます)。広域連合は、都道府県ごとに区域内の全市町村が加入して構成されます。
制度の加入者
75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入します。
なお、一定以上の障がいがある方は、加入の手続きをすると65歳から加入できます。(対象となる方には、市から案内通知を発送します)
保険料の納付者
保険料は加入者お一人おひとりから納めていただきます。
- 原則年金天引きです。ただし、世帯主等からの口座振替も可能です。
- 受給している年金額が年額18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える方は、納付書や口座振替で納めていただきます。
一部負担金
医療機関にかかったときに支払う費用(一部負担金)は、外来・入院ともかかった医療費の1割です。ただし、現役並み所得者は3割負担です。
所得区分・負担割合
| 所得区分 | 負担割合 | 所得・収入状況 |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 3割 | 同一世帯の後期高齢者医療制度の加入者の中に住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる方。ただし、「現役並み所得者」のうち、昭和20年1月2日以降生まれの加入者がいる世帯で、加入者全員の「旧ただし書き所得」の合計額が210万円以下の場合は、「一般」の区分になります。 下記に該当する方は、申請により「一般」の区分になります。
|
| 一般 | 1割 | 現役並み所得者、住民税非課税世帯以外の方。 |
| 区分2 | 1割 | 世帯の全員が住民税非課税である方。 |
| 区分1 | 1割 | 世帯の全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた各所得が0円となる世帯の方。(ただし、公的年金にかかる所得については控除額を80万円として計算) |
自己負担限度額
| 所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | |
|---|---|---|---|
| 現役並み 所得者 |
住民税課税所得 690万円以上の方 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (過去12か月間に3回以上の高額療養費の支給があった場合、4回目以降は140,100円) |
|
| 住民税課税所得 380万円以上の方 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (過去12か月間に3回以上の高額療養費の支給があった場合、4回目以降は93,000円) |
||
| 住民税課税所得 145万円以上の方 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (過去12か月間に3回以上の高額療養費の支給があった場合、4回目以降は44,400円) |
||
| 一般 | 18,000円 (144,000円上限) |
57,600円 (過去12か月間に3回以上の高額療養費の支給があった場合、4回目以降は、44,400円) |
|
| 区分2 | 8,000円 | 24,600円 | |
| 区分1 | 8,000円 | 15,000円 | |
- 現役並み所得者のうち住民税課税所得690万円未満(年収約1,160万円以下)の方が、限度額までの支払いとする場合には、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に掲示する必要があります。
- 区分1・2の方は入院の際「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので、市役所窓口に申請してください。
入院時の食事代
入院した時の食事代は、下記の区分に応じて一定額を負担することになります。
| 所得区分 | 1食当たりの食事代 |
|---|---|
| 現役並み所得者・一般 | 510円 |
| 区分2(90日までの入院) | 240円 |
| 区分2(過去12か月で90日を超える入院) | 190円 |
| 区分1 | 100円 |
療養病床に入院する場合の食事代と居住費
療養病床に入院する方は、原則として食事代と居住費を負担することになります。
| 所得区分 | 1食当たりの食事代 | 1日当たりの居住費 |
|---|---|---|
| 現役並み所得者・一般 | 510円(一部の医療機関では470円) | 370円 |
| 区分2 | 240円 | 370円 |
| 区分1 | 110円 | 370円 |
| 区分1の老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 |
保険料の徴収猶予・減免
被保険者(または属する世帯の世帯主)が災害等により重大な損害を受けたときや、属する世帯の世帯主が事業の休廃止で収入が著しく減少したとき等の予期せぬ事由により保険料を納められなくなった場合で必要があると認められるものに対し、保険料の徴収猶予・減額または免除を受けられる場合があります。
下記のいずれかの事由に該当しており、保険料の納付が難しい場合はご相談ください。
(1)被保険者(または属する世帯の世帯主)が所有し、居住している住宅、家財等が、災害により被害を受けたとき
(2)被保険者の属する世帯の世帯主が、死亡、重大な障害、長期入院、事業の休廃止や失業、干ばつや冷害等で収入が著しく減少したとき
(3)震災や水害等で広域的かつ甚大な被害をうけたとき
(4)被保険者本人が非自発的に失業したと認められるとき
(5)被保険者または被保険者であった者が刑事施設等の拘禁(収監)されたことにより、療養の給付を受けられないとき
(6)犯罪等の被害を受けたとき
申請書類
様式第47号(保険料徴収猶予申請書) [PDFファイル/82KB]
様式第52号(保険料減免申請書) [PDFファイル/77KB]
申請書の他、徴収猶予・減額または免除の原因となる内容により、各種証明書類の添付が必要です。具体的な必要書類についてはお問い合わせください。