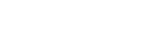本文
佐渡市教育振興基本計画(改定案)のパブリックコメントに対する佐渡市の考え方を公表します
佐渡市教育振興基本計画(改定案)に対する市民の皆さまのご意見を募集しましたところ、貴重なご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。
お寄せいただいたご意見の概要と、ご意見に対する市の考え方を公表します。
ご意見募集の概要
募集期間
令和7年1月17日(金曜日)から令和7年2月16日(日曜日)
お寄せいただいたご意見
提出者数:5人
ご意見の数:15件
提出方法:FAXでの提出1人、窓口での提出1人、メールでの提出1人、電子申請システムでの提出2人
この他、教育振興基本計画の趣旨・内容に直接関係のないご意見については、担当課に引き継がせていただきました。
ご意見の概要と佐渡市の考え方
ご意見1
学校環境整備において、市内小・中学校のトイレを完全洋式化若しくは衛生美化をお願いしたい。
幼保小の架け橋期において、担任がトイレ指導に多くの時間を割いており、子どももトイレが怖くて行き渋りする子も見られることから、心理的・生理的に安全安心な環境整備を願う。
佐渡市の考え方
市内すべての小・中学校において洋式トイレを整備しているところです。
今後も改修工事等の機会をとらえながら、洋式化の拡大に努めてまいります。
ご意見2
文部科学省が推進する「いのちの安全教育」への取組について、具体的に明記すべきではないか。
佐渡市の考え方
「生命の安全教育」については、各学校において、目の前の子どもの実態や発達の段階に応じて、教育課程内外の様々な教育活動を通じて推進することとされております。
佐渡市としての教育の大きな方針を示す当該計画に、「生命の安全教育」に関する具体的な取組を明記することはなじまないものと考えております。
教育委員会としては、各学校において適切に実施できるよう指導・助言に努めてまいります。
ご意見3
改定案が前の計画とどこが違っているのか示してほしい。
佐渡市の考え方
当該計画は、文化・スポーツの所掌が市長部局に移管することや昨今の教育に関する現状と国・県の動向等を踏まえ、今後2年間の計画として新たに策定をしております。
現行の計画との違いについて、一つ一つの変更箇所の説明まではいたしかねますが、より分かりやすく示せるように今後の研究課題といたします。
ご意見4
社会教育の重要な柱である文化やスポーツが佐渡島の金山の世界文化遺産化に伴い、市長部局の下にはぎとられることの狙いは、文化やスポーツを社会教育としての目的を「人格の完成を目指す」から佐渡観光の振興という目的に切り替えることにあると考える。その問題点として⑴社会教育の中で大きなウェイトを占める文化やスポーツが社会教育からはぎとられるという事は、例えるなら社会教育という大きな山の麓に巨大な穴が掘られるようなもので、社会教育の形がいびつであるだけでなく、社会教育の体系が崩れてくることを意味するのではないか。⑵社会教育の崇高な目的をはぎとられた文化やスポーツは単なる観光振興の手段とされ、本来の意味を失ってしまう。
社会教育法第12条に「国及び地方公共団体は、社会教育団体に対し、いかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない」とあり、社会教育の事務を司る教育委員会は地方自治法によって行政運営の公正、中立、民主化を守られており、地方公共団体の長から独立した機関として位置づけられている。これらのことから市長が社会教育から文化やスポ-ツをはぎとることは到底できないと解釈されるがもし法的に可能だとするなら、その法律上の根拠をお示しいただきたい。
佐渡市の考え方
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第23条に基づき、文化・スポーツの振興に関する事務が市長部局に移管されることになります。公民館活動をはじめとする社会教育事業については、引き続き教育委員会において推進してまいります。
ご意見5
教員の働き方改革の一環として部活動を社会体育に移行する流れが出始めているが、もし文化やスポ-ツが市長部局に移行したら、この流れは不可能になるのではないか。部活動を社会体育に移行する流れと文化やスポ-ツが市長部局に移行することとが整合性を持つとするなら、それはどのような内容になるのか、お示しいただきたい。
佐渡市の考え方
部活動の地域移行については、引き続き教育委員会が進めていくことになりますので、移管するスポーツ・文化担当部署と連携を図りながら、子どもたちが多様な文化スポーツに親しむ機会の確保に取り組んでまいります。
ご意見6
「(1) 学力等に関する各種調査の結果分析を確実に実施し」とあるが、学校現場はその調査で時間が取られ、教員の多忙化につながっている。また、子どもにとっても調査が多く、本来の学びの機会が奪われ、負担になっていることから、調査を減らす、もしくは、学校に何の調査をするか・しないかの判断をもっと委ねてはいかがか。
佐渡市の考え方
学力等の実態を把握・分析していくことは、各学校における授業改善、佐渡市の教育施策の改善のためにも重要であると考えています。その上で、学力等に関する各種調査以外の業務については、教員の負担軽減につながる方策を引き続き検討してまいります。
ご意見7
「(3)佐渡市小中学校長会や佐渡市小中学校教育研究会と連携しつつ、一人一台端末の利点を最大限に活用し、個々の学習状況の把握や家庭での学習習慣につながるよう、効果的な学びのための支援を行います」とあるが、学校現場ではICTの使用を強要され、納得できる理由がないまま遠隔での始業式や終業式の実施を校長から求められたり、長期休業中にタブレットの持ち帰りを求められたりする。欧州ではICT環境が学力低下を招いたとして、紙ベースに回帰する動きがある。ICTのもたらす負の側面にもっと目を向けて施策を考えていただけないか。
佐渡市の考え方
これからの学校教育では、1人1台端末活用も含め、児童生徒が自らの学びを自己調整していくことが求められています。そのためには、活用頻度をある程度高めたり様々な活用方法を体験したりした上で、児童生徒が主体的に活用方法や活用の有無を判断できることが大切です。活用することが目的ではなく、リアルな学びをデジタルで支えるという視点から、よりよい活用に向けて、学校、家庭、地域の理解を図れるように努めてまいります。
ご意見8
「(3)学校部活動の地域移行」ですが、各学校で部活動の削減が進んでいるのは教員の多忙化解消に向けて良いことだと思う。ただ、一概に部活動の時間を短くして、最終的には無くすのは、子どもの運動機会や仲間づくりの機会をなくすことにも繋がる。地域クラブで様々な体験機会を用意されているのはありがたいが、部活の種目によっては地域クラブに存在しないもの(環境が整っていないもの)もある。各学校の既存の部活動の種目が、地域でも取り組める環境にあるのかを学校と教育委員会とが共にチェックし、必要な環境整備に取り組んでいただだきたい。
佐渡市の考え方
部活動の地域移行(展開)を進めている途中であり、佐渡市として一律に部活動終了時間を早めることはせず、各学校の実態に応じて設定してもらうこととしております。
また、地域クラブの内容や種目の設定については、今後も生徒のニーズや地域の人的・物的資源をもとに検討してまいります。
ご意見9
「(3)キャリア・パスポート」はほぼ形骸化しているのではないか。学校現場ではその有効性を感じられない。
佐渡市の考え方
キャリア・パスポートは、児童生徒が自らの学びや経験を振り返り、将来に向けたキャリアを主体的に考えるための重要なツールとして導入されています。単に形式的に記録を残すのではなく、自己理解を深め、将来の夢や目標に向けて進んでいくためのプロセスを学校と家庭で支援していくことが大切です。キャリア・パスポートの活用が形骸化しないために、教職員を対象とした活用研修会の実施や、キャリア教育事業の充実を図っているところです。
ご意見10
「世界と共生する人材を育成する教育」とあるが、ALTやSEAの活用が、国際理解教育の充実と考えるのか?また、佐渡市はSDGs未来都市にも関わらず、この計画案の施策中にSDGsの言葉がない。ALTやSEAだけではなく、SDGsの視点をもったアクションまで試みる探究活動、世界の現状や自身とのつながりを知る学習、多文化共生、参加型学習(ワークショップ型)の充実など、もっと本腰を入れてやらなければいけない喫緊の分野だと思う。
佐渡市の考え方
ALTやSEAとの交流は、児童生徒が異なる文化や価値観に直接触れる貴重な機会と考えており、国際理解教育の充実につながっております。
また、SDGsの目標は全ての施策に関係しており、学校の教育活動や指導内容にも広く関わっています。各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間の中でSDGsの視点も入れながら、資質・能力を育成していくことが大切だと考えております。
ご意見11
学校には様々な立場の職員がいることは良いことだと思う。ただ、その費用対効果の面で考えると、大変無駄も多いと思う。それぞれの職がどれほどの役割を果たしているのかを吟味していかないと、税金の無駄遣いになるかと思う。
佐渡市の考え方
児童生徒の教育的ニーズは多様化しており、課題に対応するために、学校からの要望を聞き、様々な職員を配置しています。これからも定期的な人事評価の実施や、活動報告による勤務実態の把握など、適正な活用が図られるように努めてまいります。
ご意見12
「全国学力・学習状況調査「授業でPC、タブレットなどのICT機器を、どの程度使用しましたか」の質問に対する「ほぼ毎日」「週3回以上」の回答の割合」とあるが、使うこと自体が目的化されることを危惧する。
佐渡市の考え方
1人1台端末は個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実させるツールの1つです。児童生徒が自らの学びを自己調整していけるようにするには、ある程度の活用頻度の高さも必要と考えます。児童生徒が日常的な学習用具として活用できているかを評価するために、当該項目を指標として設定しております。
ご意見13
基本目標2 施策7に関する評価が、「小中英語教育の研修・交流」となっているが、それで「世界と共生する人材を育成する教育」を実施していると言えるのか?国際理解教育の充実に関する評価が抜けている。
佐渡市の考え方
英語教育は、国際理解教育の基盤ともなる重要な要素です。現代のグローバルな社会では、言語を通じた異文化理解やコミュニケーション能力の向上が、共生のための第一歩です。そのために当該項目を指標として設定しております。
ご意見14
ICT活用の個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実実現、一人1台端末の利点の最大限活用のため、特別教室のWi-Fi設置、教職員への端末支給をお願いする。これらの環境整備はP13の数値目標にも関わってくると思う。
佐渡市の考え方
1人1台端末の活用にあたり、Wi-Fi環境の整備は重要です。令和7年度から、特別教室のWi-Fi設置工事を順次進めていけるように計画しているところです。教職員の端末については、全員に支給していきます。
ご意見15
安全かつ教育効果を高める施設、設備の整備のため県と連携して予算確保をお願いする。体育館の電球交換、校舎内の雨漏りなど老朽化の課題は多いかと思う。また多様な子どもたちが安心して利用できるトイレの設置もお願いする。
佐渡市の考え方
児童生徒が安全安心で、かつ快適な学校生活が送れるよう、関係機関と連携して学校環境整備に努めてまいります。