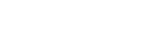本文
佐渡市 鳥獣被害防止計画(2019年2月 策定版)
2019年2月 策定、2020年2月 変更(計画年度:平成30年度〜令和2年度)
本ページの目次
対象地域、計画期間および対象鳥獣
対象地域
新潟県 佐渡市
計画期間
平成30年度〜令和2年度
対象鳥獣
カラス、タヌキ、ヒヨドリ
被害の現状
主な鳥獣による被害の現状(平成29年度)
| 鳥獣の種類 | 被害の現状 | |
|---|---|---|
| 品目 | 被害数値 | |
| カラス | 水稲 | 100万円、8ヘクタール |
| 果樹 | 200万円、2ヘクタール | |
| 野菜 | 60万円、2ヘクタール | |
| 小計 | 360万円、12ヘクタール | |
| タヌキ | 水稲 | 100万円、10ヘクタール |
| 果樹 | 150万円、6ヘクタール | |
| 野菜 | 100万円、3ヘクタール | |
| 小計 | 350万円、19ヘクタール | |
| ヒヨドリ | 果樹 | 8万円、5ヘクタール |
| 合計 | 718万円、36ヘクタール | |
被害の傾向
カラス
島内全域に生息しており、主に定植期の稲、収穫期の野菜、果樹を中心に被害が出ている。
タヌキ
島内全域に生息しており、水田畦塗り後の踏み壊しや、水稲定植後の踏み荒らしをはじめ、収穫期の野菜、果樹を中心に被害が出ている。
ヒヨドリ
島内全域に生息しており、主に収穫期の野菜、果樹を中心に被害が出ている。
被害軽減目標
| 指標 | 種類 | 現状値(平成29年度) | 目標値(令和2年度) |
|---|---|---|---|
| 被害金額 | カラス | 360万円 | 340万円 |
| タヌキ | 350万円 | 330万円 | |
| ヒヨドリ | 8万円 | 7.2万円 | |
| 合計 | 718万円 | 620.2万円 | |
| 被害面積 | カラス | 12ヘクタール | 11ヘクタール |
| タヌキ | 19ヘクタール | 18ヘクタール | |
| ヒヨドリ | 5ヘクタール | 4.5ヘクタール | |
| 合計 | 36ヘクタール | 33.5ヘクタール |
- ヒヨドリについては、10%で算出。
今後の取組方針
被害の現状
カラス、タヌキによる農作物への被害は、依然として発生しており、地域にとって被害による農業収入の減少や耕作意欲の衰退が深刻な問題となっている。また、ヒヨドリによる被害は現状として多くはないが、報告されていないものもある。
佐渡南部地域において、ルレクチェへのカラス被害が発生しており、予察などにより被害の情報収集に努め、関係機関と対策を検討する。
タヌキについては、近年疥癬症の拡大により個体数が減少し、農業被害が抑制されていたものの、再び個体数が増加傾向にある。
有害鳥獣の捕獲
地域からの被害状況を正確かつ迅速に把握し、被害発生から捕獲までの期間短縮に努める。また、有害鳥獣の個体数調査を実施し、個体数を把握するとともに調査結果に基づき必要な措置を講ずる。
捕獲については、従来どおり新潟県猟友会佐渡支部と連携し、年間を通じて捕獲できる体制を整備する。
ルレクチェへのカラス被害が発生した場合は、JA及び猟友会等と協力し早急に銃器によるカラスの駆除を実施する。
被害防止対策等の普及啓発
市やJAの広報誌や回覧板等で農家自身が簡単に対応出来る自己防衛策の方法を周知し、農家自ら被害対策を講じる意識を醸成する。
また、毎年被害の出ている地域においてはカラス被害防止に有効な防鳥クローンカラスや防鳥ネットなど農家自身が簡単に対応出来る自己防衛策を積極的に啓発し、地域や組合を挙げて自主的な追い払い体制を構築できるように促す。自主的な追い払いや対策では防げない被害は協議会所有の機材を貸し出し、被害の軽減に努める。
タヌキの対策としては農地周辺の藪や下草を定期的に刈り、隠れ場所を無くすことや、タヌキが好む果樹や野菜類を農地に放置せずに寄せ付けないような周辺の環境整備、農地の管理を徹底する。
更にはJAや猟友会等からの被害状況の聞き取りを強化し、詳細な情報の収集により効果的な対策の実施が可能となるよう、連携を強化していき、捕獲が必要な場合においても速やかに実施できるように関係機関と情報共有や連携強化を合わせて行う。
佐渡市有害鳥獣被害対策協議会
構成機関等の名称と役割は次のとおり。
| 佐渡市農業政策課 | 被害状況の把握 捕獲等申請 被害防止対策指導等 |
|---|---|
| 佐渡市環境対策課 | 捕獲等許可 保護の観点から指導 |
| 佐渡地域振興局健康福祉環境部環境センター | 被害防止対策等情報提供 指導助言 |
| (社)新潟県猟友会佐渡支部 | 捕獲作業の実施 被害状況の把握 被害防止の啓発 |
| 新潟県鳥獣保護管理員 | 鳥獣保護の観点からの助言 情報提供 |
| 新潟県農業共済組合佐渡支所 | 被害情報の把握 被害対策防止指導 |
| 佐渡農業協同組合 | 被害情報の把握 被害対策防止指導 |
| 羽茂農業協同組合 | 被害情報の把握 被害対策防止指導 |
| 学識経験者 | 指導助言 |
その他
農家・地域住民には、被害防止対策として防鳥ネット、防護柵(板柵)等の設置や農地周辺に農作物を放置せず、集落としてもゴミ処理等の管理徹底をはかるよう啓発等を行う。
効果的な被害防止対策を実施するため、農作物の被害状況、カラス類、タヌキの出没状況、防除効果等の情報の提供について協力を求める。
捕獲計画数等の設定の考え方
被害状況のアンケート調査や被害報告及び捕獲実績から推定個体数を、カラスを4,000羽、タヌキを6,000頭とする。
カラスは、依然として農作物の被害あること、及び近年の捕獲実績を踏まえ、150羽程度の捕獲を目指す。(平成29年度捕獲実績:89羽、平成30年度捕獲実績:80羽)
タヌキは、依然として農作物の被害あること、及び近年の捕獲実績を踏まえ、1,000頭程度の捕獲を目指す。(平成29年度捕獲実績:688頭、平成30年度捕獲実績:809頭)
ヒヨドリは、被害情報をもとに捕獲することとし、数値設定はしない。
捕獲計画数等
| 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | |
|---|---|---|---|
| カラス | 150羽 | 150羽 | 150羽 |
| タヌキ | 1,000頭 | 1,000頭 | 1,000頭 |
| ヒヨドリ | 被害情報を もとに捕獲 |
被害情報を もとに捕獲 |
被害情報を もとに捕獲 |
捕獲等の取組内容
カラス
銃器による捕獲(4月〜3月)島内全域(狩猟期間は狩猟可能区域)
タヌキ
ワナによる捕獲(4月〜3月)島内全域(狩猟期間は狩猟可能区域)
ヒヨドリ
銃器による捕獲(4月〜3月)島内全域(狩猟期間は狩猟可能区域)
対象鳥獣の処理方法
捕獲したカラス、タヌキ、ヒヨドリは島内クリーンセンターで焼却処分する。
その他捕獲等に関する取組
対象鳥獣は、カラス、タヌキ、ヒヨドリ。
その他被害防止に関する取組
平成30年度
各農家、地域住民に対して、被害防止対策(ネット等の設置、農作物等の適正管理)の普及啓発を実施する。(広報等で呼びかけ)
平成31年度
各農家、地域住民に対して、被害防止対策(ネット等の設置、農作物等の適正管理)の普及啓発を実施する。(広報等で呼びかけ)
果樹農家に対し、予察によるカラス被害の兆候を観察し、農家自身が対応できるよう自己防衛策を周知する。
平成32年度
各農家、地域住民に対して、被害防止対策(ネット等の設置、農作物等の適正管理)の普及啓発を実施する。(広報等で呼びかけ)
果樹農家に対し、予察によるカラス被害の兆候を観察し、農家自身が対応できるよう自己防衛策を周知する。