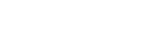本文
物価高騰支援給付金の子育て世帯への加算給付金 (子ども加算)のお知らせ
物価高に伴う影響を受けている子育て世帯への支援として、児童1人あたり2万円の給付金を支給します。
なお本給付金は、差押禁止等及び非課税の取扱いとなります。
・対象児童
・支給額
・受給方法
・Q&A
支給対象者
佐渡市から物価高騰支援給付金 (3万円/1世帯)を受給している世帯のうち基準日(令和6年12月13日)時点で18歳以下の対象児童がいる世帯の世帯主
対象児童
1 基準日時点で同一世帯となっている平成18年4月2日以降に生まれた児童
2 令和6年12月14日から令和7年6月30日までに生まれた新生児
3 基準日時点で別世帯だが、生計を同一にしている平成18年4月2日以降に生まれた児童
※ただし、以下の場合は対象となりません
・児童が令和6年度住民税均等割課税者から税法上の扶養を受けている
・児童が属する世帯の世帯主が既に本給付金(2万円の子ども加算)を受給している(ただし、令和6年12月14日から
令和7年6月30日までに生まれた児童にかかる申請を除く)
・児童が施設入所している(住民票を異動していない場合も含む)
支給額
対象児童1人あたり2万円
受給方法
手続きが不要の世帯(プッシュ型給付対象世帯)
給付金(3万円/1世帯)を受給した後、世帯構成等に変更のない場合は、世帯主宛てに順次「支給のお知らせ」を郵送しますので、記載内容をご確認ください。
※ただし、以下の場合は届出等が必要です。
(1)給付金の受給を辞退したい
受給拒否届出書の提出が必要となりますので、下記担当までご連絡ください。
(2)振込先の口座を変更したい(世帯主本人)
「支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/159KB]」の1、2欄及び誓約・同意事項欄を記入し、必要書類を添えて下記の提出先に提出してください。
(3)代理人に受給を委任したい(同一世帯員に限る)
「支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/159KB]」の1、3欄及び誓約・同意事項欄を記入し、必要書類を添えて下記の提出先に提出してください。
給付金(こども加算)の支給は、給付金(3万円/1世帯)の受給後、順次行います。
口座振込日や(1)~(3)の届出等の提出期限については「支給のお知らせ」をご確認ください。
申請書の提出が必要な世帯
次に該当する世帯は申請書の提出が必要です。申請書 [PDFファイル/289KB]
・令和6年1月2日以降に転入した世帯員がいる等により、佐渡市が世帯全員の令和6年度住民税課税状況を確認できない世帯
・令和6年12月14日から令和7年6月30までに生まれた新生児がいる世帯
・別世帯だが、生計を同一にしている児童がいる世帯 など
提出期限
令和7年7月31日(木曜日)
提出先
市役所社会福祉部子ども若者課または各支所・行政サービスセンター
Q&A
Q1: 自分の世帯が「物価高騰支援給付金(3万円)」を受給しているかわからない。
A1: 給付金窓口にお問合せください。
給付金窓口 市役所社会福祉部社会福祉課
電話0259-63-3850 (受付時間 平日8時30分~17時00分)
Q2: 児童から見て父母と祖父母で構成されている世帯において、「物価高騰重点支援給付金(3万円/1世帯)」は、世帯主である祖父が受給したが、子ども加算は父が受給することができるか。
A2: 本給付金(子ども加算)は原則世帯主に支給します。ただし、同一世帯員に限り受給委任ができますので、この場合は、祖父が父を代理人として受給を委任する届出書(「支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/159KB]」)を提出してください。
Q3: 児童が進学のため市外に住所を移し単身で寮に入っているが、支給の対象となるか。
A3: 支給対象者(世帯主)が監護し、生計を同一にする児童であれば対象になります。この場合は、申請書の提出が必要になります。
Q4: 転入前の市町村で「物価高騰支援給付金」(3万円)を受給している。令和6年12月14日以降に佐渡市に転入し新生児が生まれたが、子ども加算は佐渡市に申請すればよいか。
A4: 本給付金(子ども加算)は、先に受給した給付金に加算して支給されるものです。この場合は、転入前の市区町村(令和6年12月13日時点で住民票のあった市区町村)に出生を証明する書類を添えて申請してください。