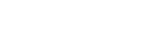本文
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
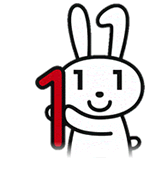
- 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について、ご説明します。
本ページの目次
本ページは、内閣官房社会保障改革担当室と内閣府大臣官房番号制度担当室が作成した資料やマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページを参考に作成しました。
ただし今後、制度の内容が変更される可能性がありますので、詳細や最新情報については、末尾のお問合せ・最新情報等をご確認ください。
市民の皆さまへ
マイナンバーとは?
- 住民票を有するすべての方に交付される12桁の個人番号のことです。
- 原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
マイナンバー制度でどう変わる?
- マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、「公平・公正な社会の実現・国民の利便性の向上・行政の効率化」などの効果が期待されます。
- 平成28年1月から、「社会保障・税・災害対策」の分野の中で、法律や条例で定められた行政手続きにおいて、マイナンバーが必要となります。
- 個人番号カードの発行(平成28年1月から)、マイナポータルの利用(平成29年1月から)が可能となります。
- マイナポータルの利用には、個人番号カードが必要となる予定です。
通知カードは廃止されました
通知カードは、法律の改正により2020年5月25日に廃止されました。廃止後は次の手続きができなくなりましたので、ご了承ください。
- 通知カードの表面記載事項(住所・氏名など)の変更
- 通知カードの再交付申請
廃止後のマイナンバー確認方法
- マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を取得してください。(1通300円の手数料がかかります)
- マイナンバーカードを申請してください。初回交付に限り、無料で作成することができます。(作成まで1か月〜1か月半程度かかります)
廃止後のマイナンバー通知方法
出生や国外からの転入により新たにマイナンバーが付番される方には、地方公共団体情報システム機構から「個人番号通知書」が郵送されます。この通知書にはマイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されています。(すでに通知カードをお持ちの方には通知書は発行されません)
- 「個人番号通知書」はマイナンバーを通知するもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合には、マイナンバーカードの提示またはマイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」の提出が必要になります。
なお、通知カードが廃止されても通知カードの表面記載事項(住所・氏名等)が住民票の記載事項と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用になれます。
個人番号カードとは?

- カード表面に、氏名・住所・生年月日・性別・顔写真が掲載され、裏面にはマイナンバーが記載されます。
- 本人確認のための身分証明書として利用できます。
- e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書(15歳未満の方は除く)の機能も搭載されます。
- 個人番号カードは、通知カードと違い申請された方にのみ交付されるカードです。当初の交付は無料ですが、交付後に紛失した場合は再交付の際に手数料が必要となります。
- 個人番号カードの有効期間は、18歳以上の方は発行後10回目の誕生日まで、未成年の方は発行後5回目の誕生日までとなります。
個人番号カードを取得するためには
- 通知カードと一緒に送付される申請書に必要事項を記載し、ご自身の顔写真を添えて返信用封筒で郵送してください。
- 申請者あてに交付通知書が郵送されますので、本人が運転免許証等の身分証明書および通知カードならびに住民基本台帳カードをお持ちの方は住民基本台帳カードを必ずお持ちになり本庁市民生活課戸籍係までお越しください。
- 住民基本台帳カード、住民基本台帳カードに搭載している電子証明書は、有効期限まで使用できますが、個人番号カードを希望される方は、交付時に住民基本台帳カードを返納し、電子証明書を失効させて、個人番号カードの交付を受けます。
- 受領の際は、個人番号カード用の暗証番号のほか複数の暗証番号の入力が必要になります。
マイナ・ポータルとは?
- インターネットを活用した情報提供等記録開示システムのことです。
- マイナ・ポータルでは、マイナンバー(個人番号)を含む自分の個人情報を「いつ、誰が、なぜ提供したのか」、行政機関が保有する自分の個人情報の内容、行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を確認できます。
- マイ・ポータルを利用する際は、なりすましによる特定個人情報の詐取予防のため、個人番号カードのICチップに搭載される公的個人認証を用いたログイン方法を採用しています。
個人情報の保護は?
- 情報を一箇所に集約して管理するのではなく、従来どおり各機関で情報を管理し、法律や条例で定められた必要な情報を必要な時だけやりとりする「分散管理」の仕組みを採用します。
- 法律や条例で決められている手続きで行政機関や勤務先などに提示する場合を除き、むやみにマイナンバーを他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不当に入手したり、提供したりすると、罰則が科せられます。
- マイナンバーを取り扱う行政機関等に対して、個人のプライバシー等の権利利益の侵害を未然に防ぐため、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。
民間事業者の皆さまへ
法人番号が指定されます
- 法人番号は13桁の番号です。
- 法人番号が指定されるのは、以下の法人です。
- 国の機関
- 地方公共団体
- 設立登記法人
- 所得税法第230条に規定する「給与支払事務所等の開設届出書」など、国税に関する法律に規定する届出書を提出することとされている、「1」〜「3」以外の法人または人格のない社団等
- 法人番号は、マイナンバーとは異なり利用範囲の制約がありません。
- 法人番号は、平成27年10月以降、国税庁長官から書面により通知される予定です。通知先は、設立登記法人は登記されている所在地、設立登記法人以外の法人等で国税に関する法律に規定する届出書を提出している法人等は届出書に記載された所在地となります。
民間事業者も、税や社会保険の手続で、マイナンバーを取り扱います
- 従業員やその扶養家族等からマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して行政機関などに提出するほか、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。
- 従業員等からのマイナンバー取得は、必ずしも平成28年1月のマイナンバーの利用開始に間に合わせる必要はなく、マイナンバーを記載した法定調書などを行政機関等へ提出する時までに取得することが必要となります。また、取得する際は、本人に利用目的(「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生年金保険届出」「雇用保険届出」等)を明示するとともに、他人へのなりすましを防止するために厳格な本人確認(次の「1」「2」の確認)を行う必要があります。
- マイナンバーが間違っていないかの確認
マイナンバーが書いてある「通知カード」や「個人番号カード」で確認 - 身元の確認
顔写真が付いている「個人番号カード」または「運転免許証」などで確認
- マイナンバーが間違っていないかの確認
- 事業者が取得したマイナンバーを、取得の際に本人に明示した利用目的や法律や条例で定められた手続き以外で利用することはできません。また、不適正に取り扱った場合、民間事業者でも処罰等の対象となります。
- 法律や条例で定められた手続き以外の事務でも、個人番号カードを身分証明書として顧客の本人確認を行うことはできますが、個人番号カードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。
マイナンバーを取り扱う際には、次の4つのルールを守りましょう。
- 取得・利用・提供のルール
- 個人番号の取得・利用・提供は、法令で決められた場合だけ
- これ以外では、「取れない」「使えない」「渡せない」
- 保管・廃棄のルール
- 必要がある場合だけ保管
- 必要がなくなったら廃棄
- 委託のルール
- 委託先を「しっかり監督」
- 再委託は「許諾が必要」
- 安全管理措置のルール
- 漏えいなどを起こさないために書類やデータは「しっかり管理」
万が一、マイナンバーが漏えいしてしまった場合には
事業者において講ずることが望まれる措置
- 事業者内部における責任者への報告、被害の拡大防止
- 事実関係の調査、原因の究明
- 影響範囲の特定
- 再発防止策の検討・実施
- 影響を受ける可能性のある本人への連絡等
- 事実関係、再発防止策等の公表
- マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、マイナンバーの変更をお住まいの市区町村に請求できることを本人に説明してください。
個人情報保護委員会または業界の所管官庁への報告
- 個人情報保護委員会に報告する場合
個人情報保護委員会ウェブサイトに掲載している様式に事実関係や再発防止策等を記載し、すみやかに個人情報保護委員会に郵送で報告するよう努めてください。(影響を受ける可能性のある本人すべてに連絡した場合、外部に漏えいしていないと判断される場合等の個人情報保護委員会への報告不要の要件をすべて満たす場合には、個人情報保護委員会への報告は不要です) - 個人情報保護法に基づき所管官庁に報告する場合
所管官庁のガイドライン等に従って、報告してください。(所管官庁から個人情報保護委員会に報告されますので、「1」の報告は不要です)
特定個人情報の安全の確保に係る「重大な事態」が生じたときに、個人情報保護委員会に報告することが法令上の義務になりました。次の事態に該当する事案またはそのおそれのある事案が発覚した場合には、個人情報保護委員会に第一報をお願いします。
「重大な事態」とは
- 漏えい・減失・毀損(きそん)またはマイナンバー法に反して利用・提供された特定個人情報に係る本人の数が100人を超える事態
- 特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を電磁的方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態となり、かつ、その特定個人情報が閲覧された事態
- 不正の目的をもって、特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を利用し、または提供した者がいる事態 等
- 個人情報保護委員会<外部リンク>>マイナンバーについて<外部リンク>>ガイドライン<外部リンク>>特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について<外部リンク>
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・受取
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報と顔写真が、裏面にマイナンバーが記載されたプラスチック製のICカードで、希望者の申請により交付されます。
公的な身分証明書として本人確認書類として利用していただけます。また、税の電子申告(e-Tax)などに必要な電子証明書が標準搭載されます。
有効期限は、発行日から10回目の誕生日までです。ただし、20歳未満の人は、容姿の変化を考慮し、発行日から5回目の誕生日までです。電子証明書の有効期間は発行日から5回目の誕生日までです。
マイナンバーカードの詳しい説明は、マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご覧ください。
住所変更等の届出には、変更する全員分のマイナンバーカードをお持ちください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・受取方法
申請する際、または、受け取る際、いずれか1度はご本人に市役所へお越しいただく必要があります。
- 受け取る際に、市役所へお越しいただく方法
申請方法は郵送またはインターネットとなります。(市役所で申請することもできます) - 申請する際に、市役所へお越しいただく方法
受取方法は郵送となります。
マイナンバーカードの交付手数料
初回発行手数料は当面の間、無料とされています。
再交付手数料は1,000円(個人番号カードが800円、電子証明書が200円)です。
その他
マイナンバーカードの申請・交付手続きには、15分〜20分程度かかります。週明けは混雑することが予想されますので、目安時間は30分以上になることもありますがご了承ください。
交付状況
現在、マイナンバーカードは、申請していただいてからお受け取りできるまで、1か月〜1か月半程度かかります。カードの交付の準備が整い次第、交付通知書(はがき)を郵送しますので、はがきが届くまでしばらくお待ちください。
- 今後の申請件数の推移により、発送日時が前後する可能性があります。
お問合せ・最新情報等
マイナンバー制度 関連ホームページ
- 政府広報オンライン<外部リンク>>IT・デジタル<外部リンク>>マイナンバー<外部リンク>
- 総務省<外部リンク>>番号制度に係る地方税の業務について<外部リンク>
- 厚生労働省<外部リンク>>社会保障・税番号制度(社会保障分野)<外部リンク>
- 国税庁<外部リンク>>社会保障・税番号制度について<外部リンク>
- 個人情報保護委員会<外部リンク>
- 地方公共団体情報システム機構<外部リンク>>個人番号カード総合サイト<外部リンク>
- 独立行政法人国民生活センター<外部リンク>>マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください!<外部リンク>
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
平日の9時30分〜22時と、土日祝の9時30分〜17時30分(12月29日〜1月3日を除く)
- 2016年4月1日以降は平日の9時30分〜20時00分と、土日祝の9時30分〜17時30分(12月29日〜1月3日を除く)の対応となります。
- かけ間違いのないようにご注意ください。
- 「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
- 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
- 既存のナビダイヤルも継続して設置しております。こちらの音声案内でもフリーダイヤルを紹介しています。
- 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、下記へおかけください。(有料)
- マイナンバー制度に関すること:050-3816-9405
- 「通知カード」「個人番号カード」に関すること:050-3818-1250
- 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
- マイナンバー制度に関すること:0120-0178-26
- 「通知カード」「個人番号カード」に関すること:0120-0178-27
マイナンバーコールセンター(制度に関するお問い合わせ)
0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)(通話料がかかります)
平日の9時30分〜22時と、土日祝の9時30分〜17時30分(12月29日〜1月3日を除く)
- 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、「050-3816-9405」へおかけください。
- 外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)は「0570-20-0291」へおかけください。
中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応については、平日の9時30分〜20時と土日祝9時30分〜17時30分になります。
通知カード・個人番号カードセンターに関するお問い合わせ
0570-783-578(全国共通ナビダイヤル)(通話料がかかります)
平日の8時30分〜22時と、土日祝の9時30分〜17時30分(12月29日〜1月3日を除く)
- 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、「050-3818-1250」へおかけください。
- 個人番号カードの一時利用停止については24時間365日受け付けます。
法人番号に関するお問い合わせ
0120-053-161
平日の9時〜17時(土曜・日曜・祝日と、12月29日〜1月3日を除く)
- 法人番号管理室では、国税に関するご相談は行っていません。
- 税務相談については、最寄りの税務署へ電話でご連絡していただくか、国税庁ホームページのタックスアンサー(よくある税の質問)<外部リンク>をご利用ください。
- ご参考:法人番号管理室の所在地・電話番号<外部リンク>
マイナンバー制度に便乗した詐欺にご注意ください
マイナンバー制度に便乗した新種の詐欺が報告されています。マイナンバーに関して、国や自治体の職員が家族構成や資産・年金・保険の状況等を聞くことはありません。だまされないようにご注意ください。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
- 独立行政法人国民生活センター<外部リンク>>マイナンバー制度に便乗した詐欺に注意<外部リンク>
- 独立行政法人国民生活センター<外部リンク>>マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください!<外部リンク>
担当窓口
- 本ページ全般について:市役所 本庁舎 市民課 戸籍係(0259-63-5112)
- 特定個人情報保護評価について:市役所 本庁舎 総務課 総務行革係(0259-63-3111)