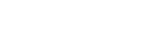本文
令和2年 第5回(6月)定例会の一般質問通告表
令和2年 第5回(6月)定例会
- 印刷用には一般質問順位表[PDFファイル/92KB]と一般質問通告表[PDFファイル/445KB]をご利用ください。
本ページの目次
一般質問順位表
6月18日(木曜日)
| 順位 | 氏名 | |
|---|---|---|
| 午前 | 1 | 広瀬大海 |
| 午後 | 2 | 室岡啓史 |
| 3 | 佐藤定 | |
| 4 | 中川健二 |
6月19日(金曜日)
| 順位 | 氏名 | |
|---|---|---|
| 午前 | 5 | 山田伸之 |
| 午後 | 6 | 北啓 |
| 7 | 山本健二 | |
| 8 | 後藤勇典 |
6月22日(月曜日)
| 順位 | 氏名 | |
|---|---|---|
| 午前 | 9 | 荒井眞理 |
| 午後 | 10 | 稲辺茂樹 |
| 11 | 中川直美 | |
| 12 | 中村良夫 |
6月23日(火曜日)
| 順位 | 氏名 | |
|---|---|---|
| 午前 | 13 | 近藤和義 |
一般質問通告表
順位:1、 質問者:広瀬大海
6月18日(木曜日)午前
- 渡辺市長の「やりたいこと」は何か
- 選挙で訴えてきた内容と所信表明について
- 職員不祥事の再発防止策について
- withコロナ、アフターコロナ時代を見据えた健康対策と経済対策について
- 新型コロナウイルス感染拡大防止のための健康寿命延伸の推進を
- 予防医療の方針と取り組み状況は
- 口腔ケアの推進と「佐渡市歯科口腔保健推進条例」制定を
- 新型コロナウイルスによる暮らしや心の変化に対応した経済対策と雇用確保を
- 新型コロナウイルスによる経済的影響と雇用の状況は
- 佐渡市民の一人当たりの所得はいくらか
- 島内企業向け支援の方針は
- サテライトオフィスの誘致と起業支援の実績は
- 特定地域づくり事業協同組合の活用を予定しているのか
- 観光業・飲食業の再生には佐渡クリーン認証制度の総力をあげたPRが必要では
- 余暇の過ごし方の変化によるアウトドアレジャーの整備・推進を
- 若者の島外への流出抑制、UIターン増のための若者の活躍・交流の場の整備を
- 婚姻数の増加と理想とする子どもの人数をもうけることができる支援を
- 新型コロナウイルス感染拡大防止のための健康寿命延伸の推進を
順位:2、 質問者:室岡啓史
6月18日(木曜日)午後
- 持続可能な地域づくりの実現に向けて
【しごとづくり】【ひとづくり】【まちづくり】の計画に関する確認と提案- 新型コロナウイルス対策を踏まえた「新しい生活様式」について
- 佐渡市の財政状況と令和2年度の補正予算による反転攻勢
- 市民および島内事業者(法人・個人)への支援策
- 小中学校・執行部・議会へのタブレット(電子機器端末)導入
- 持続可能な地域づくりについて
- ソフト・ハード両面の防災減災対策による安全安心な島づくり
- オンライン観光や地域の情報化による観光地域づくり
- コロナ後の生き方を見直すUIターン促進による人口減少対策
- 佐渡金銀山の世界文化遺産登録について
- 新潟県内唯一の世界遺産登録という記念日を条例制定へ
- さどまる倶楽部会員10万人、関係人口100万人創出への礎として
- 国連のSDGs(持続可能な開発目標)の取り組みをSaDoGsへ
- 新型コロナウイルス対策を踏まえた「新しい生活様式」について
順位:3、 質問者:佐藤定
6月18日(木曜日)午後
- 地方自治法等の一部改正に伴う佐渡市としての対応について
- 「内部統制の制度化」、「監査の実効性や独立性の向上」など、ガバナンスのあり方について
- 内部統制に関する方針の策定等について、佐渡市は努力義務の自治体となっているが、地方自治法第2条第14項、第15項、第16項等の趣旨から、「ア 業務の有効性・効率性の確保」、「イ 財務報告等の信頼性確保」、「ウ コンプライアンスの確保」、「エ 公有財産の適切な管理・保全・活用の推進」に前向きに取り組むべきである。早期に制度を導入する必要があると考えるが、市長としてどのように考えているか
- 併せて、内部統制を前提とした監査を実施することにより、合規制、経済性、効率性、有効性が図られると推察するが、市長としてどのように考えているか
- 損害賠償請求関係について
職員等の地方公共団体に対する損害賠償責任で、重過失がない場合に条例で責任額を定めることについて、どのように整理するか
- 「内部統制の制度化」、「監査の実効性や独立性の向上」など、ガバナンスのあり方について
- 地域人口の減少対策として、本年6月に施行された「特定地域づくり事業協同組合制度」を活用した地域社会の維持及び地域経済の活性化に、市としてどのように取り組むのか
- この制度は単に人口減少対策だけではなく、新たな仕事づくりなどさまざまな波及効果を生み出す制度である。市長としてこの制度を活用したグランドデザインがあれば、考え方を示せ
- 事業協同組合の構成員は、島内の農林漁業・製造業等・サービス産業などの事業所が対象となるが、受け皿となる新たな事業協同組合の設立・運営について、市としてどのように関わっていくのか
- 地区外からの移住者の呼び込みと定着化について、どのような施策を講じるのか
- 地区内の若者たちの就業先としての位置づけはどのように考えるか
- 平成29年3月に変更された佐渡市将来ビジョンの計画期間最終は令和元年度末となっているが、新たな将来ビジョンの提案はいつになるのか
- 「佐渡市将来ビジョン」「佐渡市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の目標年次の総括はどのようになっているか
- 第2次将来ビジョンの策定にあたり、市民意見交換会の参加人数が少なく、市民参加のビジョンとなっていない。再度、市民の意見を聞くべきと考えるが、どうか
- 前市政のときに示された第2次将来ビジョン基本構想(案)は、国連で採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」の理念に基づいたものとなっている。11番目の目標「住み続けられるまちづくり」の達成手段として「地域の困りごとを解決する仕事づくり」をJA・生活協同組合・社会福祉協議会などと連携した協同労働組織(おたがいさま等)を育成し、住民力に基づく持続可能な佐渡市を目指すことについて、市長はどのように考えているか
- 持続可能な農業と食育について
- 新たな米政策が平成30年から始まり、需要に応じた米の生産を生産者自身で行っているが、2年が経過して見えてきた課題は生産調整が超過達成していることである。結果、需要があるのに販売機会を失っている現状を市長はどのように受け止めているか
- 佐渡市認証米を学校給食で提供しているが、給食で提供されるご飯がセンター方式のため、本来の美味しさが損なわれている。学校現場で家庭用炊飯器により炊飯を行い、子どもたちに日本一美味しい「佐渡米」を美味しい状態で食べさせることができないか。また、調理の一部分を子どもたち自身で行うことによる食育ができないか
順位:4、 質問者:中川健二
6月18日(木曜日)午後
- 佐渡航路の安定と充実
- 小木航路のダイヤは、観光はもちろんのこと、島民の利便性も基本となるべき
- 乗船割引の対象者を島外利用者にも拡大すべきではないか
- 小木〜直江津航路で不評の「あかね」を赤泊〜寺泊航路に就航させることはできないか
- 佐渡の宝である一次産業の活性化
- 農業の活性化
- 集落営農、大規模農業、複合化のモデルとはどのようなものか
- 農業公社には連携する組織が必要ではないか
- 後継者育成のためにも販売を強化する施策が必要ではないか
- 漁業の活性化
- 後継者を育成するために何が必要か
- 販売強化に向けて何が求められているか
- 林業の活性化
- 森林環境譲与税の有効活用の具体策はあるか
- 島内の豊富な森林を地産地消するためには何をすべきか
- 農業の活性化
- 屋外防災無線の動作確認のルール作りが必要ではないか
順位:5、 質問者:山田伸之
6月19日(金曜日)午前
- 国の第2次補正予算案における市の新型コロナウイルス対策について
- 事業継続と雇用を守り抜く支援
- 雇用調整助成金や持続化給付金の給付状況について
- 資金繰り支援としての「劣後ローン」の活用について
- 家賃支援給付金について
- 暮らしを守り抜く支援
- ひとり親世帯への臨時特別給付金について
- 学校再開における感染症対応と人的体制の確保について
- 医療及び介護へのさらなる支援
緊急包括支援交付金の活用による体制の強化について - 地方へのさらなる支援
地方創生臨時交付金の活用について
- 事業継続と雇用を守り抜く支援
- 市長の所信表明について
佐渡の航空路開設、首都圏・関西圏便の実現について
順位:6、 質問者:北啓
6月19日(金曜日)午後
- 消毒作業員、スクール・サポート・スタッフの配置について
小学校、中学校での新型コロナウイルス感染症対策として、消毒作業員の配置、スクール・サポート・スタッフを配置すべきと考えるが、どうか - 佐渡市奨学金制度について
現制度は市が奨学金の貸与を行い、学校を卒業した後10年の間に佐渡に定住し、継続して5年間就労すると奨学金の返還が免除になる制度だが、奨学金を貸与する制度と、奨学金を交付する制度と2つに分け、Iターン者にも対応できるように制度の変更・拡充をすべき - 働きやすい職場の環境づくりについて
子育てや介護を仕事と両立している従業員に対し、仕事との両立支援を積極的に推進するきっかけ作りを目的として、民間企業と市役所が連携した応援制度を実施すべきと考えるが、どうか
順位:7、 質問者:山本健二
6月19日(金曜日)午後
- 防波堤等漁港施設の開放について
市民や観光客の釣り場所にすべきではないか - 公園・テニスコート・野球場等の管理体制について
草刈り等をポイント制にすべきではないか - 真野体育館・公民館は存続すべきではないか
- 市所有の山を利用して山菜採りや椎茸栽培を行い、収穫した食材を使用して調理実習などの体験学習をすべきではないか
- 高齢者や弱者の交通について
車の運転免許証を所有していない方のために通院や買い物の支援が必要ではないか - 佐渡汽船について
- 新幹線の時刻表に合わせるべき
- ジェットフォイルは3隻必要か
- 新潟交通佐渡について
- 佐渡汽船とバスとの時刻表を合わせるべき
- バス停留所の通過予定時間を守らせるべきではないか
順位:8、 質問者:後藤勇典
6月19日(金曜日)午後
- 新型コロナウイルス対策としての医療のあり方について
- 有事を想定した図上訓練は実施済みか
- 医療備品のリアルタイムな在庫把握ができているか
- 医療従事者の人手不足に対してどのように対応していくか
- 介護施設でクラスターが発生した際の医療機関との連携について
- 市長所信表明「遠隔医療の体制整備」の見解について
- 防災対策について
- 地域防災計画は、新型コロナウイルス対策を盛り込んだものに更新させる必要があるが、見直しはいつ実施する予定にあるか
- 避難所における感染症対策としてのゾーニングについて
- 避難所における段ボールベッドの配備について
- 宿泊施設との災害時応援協定について
- 新型コロナウイルス対策を想定した防災訓練の実施について
- BCP(事業継続計画)について
- 事業所に対する事業継続計画書作成の支援について市長の考えを問う
- 罹患者情報の公表について
- 消毒経費の支援について(濃厚接触が疑われた事業所など)
- 市のゴミ処理事業に対するBCPについて
- 公衆衛生について
- 水際対策としての個人情報の取得、各施設における個人情報の取得について、現状の把握と改善点について市長の考えを問う
- 事業所における三密対策の現状と今後の周知徹底について
- 佐渡クリーン認証制度の継続的なブラッシュアップと継続的な周知徹底について
- 観光地におけるマスクごみのポイ捨て対策について
- 経済等の対策について
- これまで実施してきた施策の課題・改善点について市長の考えを問う
- プレミアム商品券の実施について
- 子育て支援策・移住定住支援策・若者定住支援策について
- 佐渡空港について
順位:9、 質問者:荒井眞理
6月22日(月曜日)午前
- 人が人らしく生きられる佐渡を実現するために
- 人が生き生きする佐渡の社会をつくること
- 出生数激減を早急に食い止めるためにすべき事業の充実と誰にとっても楽しい子育て環境を充実させるため、佐渡市子育て支援事業を急加速で実現すること
- 「孤育て」や子育てに自信のない親の解消のため、親育ちのための事業を早急に充実させるべき
- 県の児童相談所に保護されている佐渡の子どもは多いと聞く。児童相談所との連携を強化し、保護される子どもが一刻も早く佐渡に帰ってこられる体制を整えること
- 子育て世代のニーズをアンケートや聞き取りで把握すること
- 一人のニーズに対しても事業を立ち上げ、専門的な担当職員を配置すること
- 必要な専門職配置、予算倍増の措置などを早急に進めるべき
- 障がい福祉政策を全面的に取り上げ、前進させること
渡辺新市長の所信表明には、歴代市長と同じく障がい福祉政策にほとんど触れられていなかったが、社会的に弱くされている分野こそが社会のセーフティーネットである。新市長の障がい福祉政策を改めて問う- 「私たちのことは私たち抜きで決めないで」という障害者の権利条約のスローガンを尊重し、障がいのある当事者の意見を吸い上げる仕組みを立ち上げること
- 障がい毎の当事者活動団体を市の音頭で立ち上げること
- 障がい者雇用は停滞している。推進するため、支援団体の体制強化を支援すること
- 出生数激減を早急に食い止めるためにすべき事業の充実と誰にとっても楽しい子育て環境を充実させるため、佐渡市子育て支援事業を急加速で実現すること
- コロナ禍対策
誰もが安心して活動を続けられる体制の強化が、ひいては経済活動の停滞を抑えることにもつながることからも、コロナ禍で浮き彫りにされた弱い分野を徹底的に強化すべきである- PCR検査や抗体検査体制を島内で早急に整えるべき
- 妊娠時の免疫力低下から女性たちを守るための対策を打つべき
休業支援やオンライン診療の推奨 - 放課後等デイサービスの拠点施設を増設すること
- 外国籍住民に対して外国語での情報提供を確保すべき
- オンライン授業の導入は学校と家庭の現状をアンケートで確実に把握した上で、無理のない、しかも必要に応じて対応するよう慎重に進めるべき
- 重度の障がいがある住民が利用できる施設の拡充
- 将来ビジョンは未完成であるが、新市長体制に入り、これをどうするのか方針を問う
- 合併以来、佐渡のまちづくり地区区分の議論は中途半端に終わっている。将来を見据えたまちづくり議論を正面から始めるべきと考えるが、新市長の方針を問う
- 残された合併特例債をどのようにする考えか、新市長の方針を問う
- コロナ禍にあって公立病院の位置づけが定まらないが、両津病院の建設計画についての新市長の見解を問う
- ゼロカーボンアイランド宣言に基づく洋上風力発電計画についての新市長の見解を問う
- 佐渡文化財団の2年間の評価は非常に低く解散に値するのではないかと考えるが、この財団のこれまでの活動の評価と存在意義、今後の補助金事業としての新市長の方針を問う
- 佐渡の博物館行政について
- 博物館ビジョン策定のためには、各分野の学芸員を策定員に必ず加えるべきと考えるが、どうか
- 一般職で採用している学芸員を、学芸員として任命し直すなど、専門性を活かした現場体制を早急に確立すべきと考えるが、どうか
- 除雪費のあり方が不透明である。今年の冬は明らかに暖冬であったが、その実績などを踏まえながら、透明で公平な委託事業の執行に務めるべきと考えるが、新市長の見解を問う
- 佐渡市に公立の認定こども園が必要と考えるのか、新市長の見解を問う
- 人が生き生きする佐渡の社会をつくること
順位:10、 質問者:稲辺茂樹
6月22日(月曜日)午後
- 新型コロナウイルスの現状とこれからの対応について
- 給食の有機食材導入について
- 第5期中山間地域等直接支払制度移行に伴うアンケート調査結果の検証について
- 佐渡文化財団のこれまでの経緯とこれからについて
- 個別施設計画における考え方と今後の進め方について
順位:11、 質問者:中川直美
6月22日(月曜日)午後
- 市政運営の基本と重要計画について
- これまでの新型コロナウイルスへの国、県の対応についての見解及び今後の市としての対応
- 所信表明において述べている「弾力的な組織」、「組織改革」、「ワンチーム佐渡」の具体的な取り組み方向
- 行政の基本になる最上位計画、新市建設計画に基づく合併特例債活用計画、公共施設等総合管理計画、個別施設計画、高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画、行政改革計画等、各種計画への取り組みについて
- 行政と市民との関係構築のために市民参加条例を制定すべきではないか
- 佐渡航路の船舶更新について
- 離島佐渡にとって生命線であり、公共交通でもある佐渡航路で就航しているジェットフォイルの新造船建造について、約34億円の建造費に対して大株主の新潟県が佐渡市へ同等となる3.4億円の負担を求めているが、どうなったか。今後、カーフェリーの更新で建造費60億円が見込まれるが、新潟県の姿勢はどうか
- 改正離島振興法などの流れの中、今回の新潟県の対応は問題ないか
- 新型コロナウイルスによる航路等への影響は深刻であり、小手先で解決できるものではないが、どのように対応するのか
- 佐渡文化財団の事務不適正処理事案から教育行政は何を学んだのか
- 佐渡文化財団設立に伴う諸問題についての監査結果は、それを待つまでもなく明らかなものばかりだが、これまでの公式の場での答弁等と矛盾していないか
- この問題の根本問題を教育委員会の組織として、どう捉えたのか
- 5月29日付「職員の事務不適正に係る懲戒処分等について」による職員の戒告処分、教育長の譴責処分は問題ないか
- 監査委員の「市長の要求に基づく監査の結果」の結論は、「設立準備負担金の使途及び事務執行は、適正に行われていなかった」、「文化財団補助金に係る事務執行は、適正に行われていなかった」としているが、補助金等を申請しながらルールに反した使い方をした佐渡文化財団をこのまま放置して問題はないと考えているのか
順位:12、 質問者:中村良夫
6月22日(月曜日)午後
- 新型コロナウイルスの感染から市民の命と暮らしを守ることについて
- 公立・公的病院である新両津病院の建設計画について
厚生労働省が公開した公立・公的病院の再編・統合リストの問題点と新両津病院の建設、岩首診療所をはじめ、各診療所の存続と巡回診療継続の認識について - 資格証明書交付世帯の受診機会が確保できるよう、短期保険証の速やかな交付を求める
- 補聴器購入の補助制度創設について
耳が聞こえにくかったり、聞こえなかったりすることが高齢者の社会参加等への大きな障がいとなっている。高齢になっても生活の質を落とさず、心身ともに健やかに過ごすことができれば、認知症の予防、健康寿命の延伸、ひいては医療費の抑制にもつながるため、加齢による難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める - 経済波及効果が高い住宅リフォーム助成制度の復活を求める
- 学校給食の無償化を求める
- 就学援助制度のさらなる拡充について
- 申請期間を延長し、家計が急変した場合には年度途中でも速やかに認定すべき
- 休校中の昼食代を補助すべき
- 卒業アルバム代を補助の対象とすべき
- 新入学準備金の支給は入学前の3月から前年の12月に変更すべき
- 就学援助基準を生活保護基準の1.5倍にすべき
- すべての家庭に直ちに周知すること。また、簡易な手続きに改め、必要な援助がすぐに実施されるよう対応すること
- 公立・公的病院である新両津病院の建設計画について
順位:13、 質問者:近藤和義
6月月23日(火曜日)午前
- 少子化対策の成功自治体すべてが実施している出産祝金制度創設は必要不可欠
市長公約の「第3子に最大300万円の子育て支援」の実施(給付)はいつからか - 合併特例債による本庁舎建設
- 建設の内容(規模)と今後のスケジュール
- 市長所信表明の「雨天・荒天時の屋内での子どもの遊戯場所の確保」は、新庁舎に包含(併設)すべきではないか〔例:日本建設業連合会表彰の新発田市庁舎 令和元年7月〕
- 農業政策
- 仲之入(なかのいり)地区及び尾嵩郷内(おだけごうち)地区の、ため池等整備事業に伴う受益地の1年間全面不耕作に対する市の支援策
- 市長が手掛けた「トキ認証米」は佐渡米ブランドとして評価するが、当初の農家への60キログラム当たり1,500円加算の仕組みが達成されていないことに対する改善策
- 市長は所信表明で「農業の大規模化等の体制づくりへの支援策」を述べているが、本市農家の98.4%を占め、SDGsでも主体として位置づけられている家族農業への支援策は何か
- 会計年度任用職員の期末手当の支給は、総務省の事務処理マニュアルを踏まえ、2.6月にすべきではないか
- 格安航空会社(LCC)新設構想に対する市の対応
- 介護地獄・介護離職防止のために特養の増設・増床が必要ではないか
- 新型コロナウイルスの感染防止と経済対策の本市の取り組み状況