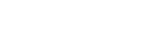本文
令和2年 第7回(9月)定例会の一般質問通告表
令和2年 第7回(9月)定例会
- 印刷用には一般質問順位表[PDFファイル/96KB]と一般質問通告表[PDFファイル/488KB]をご利用ください。
本ページの目次
一般質問順位表
9月9日(水曜日)
| 順位 | 氏名 | |
|---|---|---|
| 午前 | 1 | 林純一 |
| 午後 | 2 | 山田伸之 |
| 3 | 佐藤定 | |
| 4 | 中村良夫 |
9月10日(木曜日)
| 順位 | 氏名 | |
|---|---|---|
| 午前 | 5 | 中川健二 |
| 午後 | 6 | 平田和太龍 |
| 7 | 山本健二 | |
| 8 | 北啓 |
9月11日(金曜日)
| 順位 | 氏名 | |
|---|---|---|
| 午前 | 9 | 中川直美 |
| 午後 | 10 | 上杉育子 |
| 11 | 駒形信雄 | |
| 12 | 後藤勇典 |
9月14日(月曜日)
| 順位 | 氏名 | |
|---|---|---|
| 午前 | 13 | 荒井眞理 |
| 午後 | 14 | 稲辺茂樹 |
| 15 | 近藤和義 |
一般質問通告表
順位:1、 質問者:林純一
9月9日(水曜日)午前
- 防災拠点庁舎建設について
- 新庁舎完成まで、現庁舎における震災時の対策及び対応はどのようになっているのか
- 建設費約30億円の公共投資による島内への経済効果の試算はどうか
- 本庁舎への機能集中に伴い、所信表明で述べた支所・行政サービスセンター機能の拡大方針に変わりはないか
- 移住交流政策について
- 所信表明で述べたプロジェクトの進捗状況はどうか。コロナ禍が続く今、具体的施策の実行がないと効果が薄れてしまうのではないか。また、全国区での競争としては遅くないか
- テレワーク、リモートワーク、ワーケーション等が注目される中、都市部からの誘致に関して当市の取り組みはどのようになっているのか
- 二地域居住施策の強化が必要ではないか(交流人口拡大→関係人口拡大→二地域居住者の拡大→移住定住者の拡大というプロセスを前提として)
- 佐渡文化財団について
- 新体制による本年度事業の今までの進捗状況及び年度内の見込みはどうか
- 現在の課題は何か
- 来年度に向けた方針や目標について、どのように考えているのか
- 空路再開について
- 経済誌にも積極的意向が記載されているが、市長の考えを再度問う
- 空路再開及び羽田空港就航までには相当高いハードルが想定されるが、そのための実行計画(5年間程度のロードマップ)はどのようになっているのか
- 今後の市としての具体的な実行計画とスケジュールを問う
- 新型コロナウイルス対策について
- 今まで実施してきた各種経済支援施策の進捗状況及び成果はどうか。特に、宿泊、飲食関連、温泉施設はどのような状況と捉えているか
- 6月定例会の代表質問時には保留となっていた経済指標のKPIは何にしたのか。それによる分析等はあるのか
- 島の経済状況がどのような状況になるまで対策を継続するのか。追加施策について、今後の方針を問う
順位:2、 質問者:山田伸之
9月9日(水曜日)午後
- 新型コロナウイルス感染症対策について
- 医療分野
- インフルエンザワクチン接種の促進
- 発熱外来の受け入れ体制
- 老人福祉施設でのクラスター対策
- 国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の減免実績
- 観光分野
- 7月、8月の入込数とGo To キャンペーンの評価
- 観光施設の感染予防物資の継続的な支援と拡充
- 県民限定宿泊施設と島民限定日帰り入浴促進事業の実施について
- 教育分野
- 修学旅行に行く予定の学校数と行先、感染防止対策
- 修学旅行の受け入れ予定と受け入れ体制の整備
- 低所得世帯へのWi-Fi通信料の支援
- 避難所体制
- コロナ禍を見込んだ避難所運営マニュアルの策定
- 広域避難所となる学校体育館のエアコン設置
- 医療分野
- 空き家対策について
- 空き家の活用促進と改修支援
- 大型老朽化危険廃屋の解体促進
順位:3、 質問者:佐藤定
9月9日(水曜日)午後
- 市民から信頼される市役所づくりについて
- まちづくりは市民、議会、市がそれぞれの責任と主体性によって、対等な立場で相互に理解し、信頼関係のもと協働して行うものと理解している。内部統制は、行政サービスでの市民の福祉の増進を阻害する要因をリスクとして能動的に捉え、組織的にコントロールするものである。この内部統制を主体的に担う職員の置かれている状況について問う
- 「第3次集中改革プラン」総括の「定員管理と給与の適正化」の項によれば、定員適正化の進捗状況は計画を上回るスピードで進行している。それにもかかわらず、管理する施設数や事務事業数の削減が進まず臨時職員の増加により対応していると指摘されているが、適正な事務処理や労務管理はできているか
- 「人材育成基本方針」については、佐渡市合併当時の平成16年度に策定されたが、以後、変更や更新がされていない。適宜、各種研修を行っているが、このような状態で市民の期待に応えられる職員の育成が可能なのか
- 市民指向型意識の醸成の箇所にある「業務改善運動の推進」について、当初は力を入れて実施したが、年を経過するごとに尻つぼみとなり、当初の目論見どおりになっていないと総括している。それにもかかわらず、「職員意識調査」「地域活動参加」など、職場風土の改善において重要と思われる項目については調査継続不要と総括されているが、不要と考えているか
- 本定例会の報告第14号、専決処分の報告について
今回の事務手続きはマニュアル等に沿った手続だったのか。また、発生原因と事務ミスを発生させた要因は何か
- まちづくりは市民、議会、市がそれぞれの責任と主体性によって、対等な立場で相互に理解し、信頼関係のもと協働して行うものと理解している。内部統制は、行政サービスでの市民の福祉の増進を阻害する要因をリスクとして能動的に捉え、組織的にコントロールするものである。この内部統制を主体的に担う職員の置かれている状況について問う
- 学校健康診断における近見視力検査の意義と導入について
- 令和2年6月定例会において、国の「児童生徒1人1台端末整備」の前倒し支援に伴い、小中学校に端末を整備する予算が計上された。これにより、学習の形態は黒板中心からタブレット端末中心へと変化していくと考えられる。現在、行われている視力検査では、黒板の文字等は判別できるが、近くの対象物を判別できない児童生徒が一定数学校現場に存在していると研究者から指摘されている
- 導入されるタブレット端末を利用して、どのような授業を行うのか
- 佐渡市での小中学校視力検査はどのような検査か。また、現在の検査方法で不都合な点はないか
- タブレット端末の利用により、遠くにある黒板の文字を判読する「遠見視力」とは別に、近くの画面の文字を判読する「近見視力」が必要となってくる。教育の平等性確保の観点から児童生徒の視力実態調査をすべきと思料するが、どうか
- 令和2年6月定例会において、国の「児童生徒1人1台端末整備」の前倒し支援に伴い、小中学校に端末を整備する予算が計上された。これにより、学習の形態は黒板中心からタブレット端末中心へと変化していくと考えられる。現在、行われている視力検査では、黒板の文字等は判別できるが、近くの対象物を判別できない児童生徒が一定数学校現場に存在していると研究者から指摘されている
- 世界農業遺産の維持・発展について
- 令和2年6月定例会の一般質問で、中山間地域での耕作放棄地について質問した。「このまま耕作放棄地が拡大し、中山間地域の景観が維持できない場合は、世界農業遺産の認定から外れるかもしれない」との答弁であったが、棚田地域振興法等を活用した中山間地域の水田耕作の維持について問う。また、「朱鷺と暮らす郷づくり」認証制度について、2007年発足以来定着してきたが、時代としてオーガニック志向の流れがある。そのため、品目については水稲以外の野菜・果樹等への拡大、栽培方法については有機栽培や自然栽培など、次の段階に進むべきと考える
- 佐渡市での指定棚田地域の数と面積はどのようになっているか。また、耕作が放棄されている面積等はどのくらいか
- 県の段階で作成した「棚田地域振興計画」を受けて、佐渡市での棚田地域振興計画が作成されているか。作成されている場合は、どのような内容か
- 棚田地域は急傾斜地などの耕作条件不利地であるため、耕作維持の道路整備や小規模土地改良、ドローン導入等の助成制度により棚田の保全を図れないか
- JA佐渡では水稲栽培でのネオニコチノイド系農薬を使わない取り組みを実施している。このことは、ネオニコチノイド系農薬の危険性の回避や、トキ放鳥による自然繁殖を後押するなど、佐渡島全体を世界農業遺産にふさわしい環境にする取り組みを実践しているが、佐渡市としてネオニコチノイド系農薬の使用について、どのように捉えているか
- 令和2年6月定例会の一般質問で、中山間地域での耕作放棄地について質問した。「このまま耕作放棄地が拡大し、中山間地域の景観が維持できない場合は、世界農業遺産の認定から外れるかもしれない」との答弁であったが、棚田地域振興法等を活用した中山間地域の水田耕作の維持について問う。また、「朱鷺と暮らす郷づくり」認証制度について、2007年発足以来定着してきたが、時代としてオーガニック志向の流れがある。そのため、品目については水稲以外の野菜・果樹等への拡大、栽培方法については有機栽培や自然栽培など、次の段階に進むべきと考える
- 県立高校等再編整備計画における「佐渡中等教育学校のあり方について検討する」について
- 令和2年6月新潟県議会定例会での総務文教常任委員会において、令和5年度に佐渡中等教育学校の募集を停止し、佐渡高校と統合するとの再編計画が示された。その後、渡辺市長や県議会総務文教常任委員会などの取り組みにより、令和2年7月県立高校等再編整備計画では募集停止の記載が削除されたが、「佐渡中等教育学校のあり方について検討する」との事項が追加された
- 市長は島内高校のあり方について、「新潟県教育委員会へ提言することを前提に検討を進める」と発言したが、市長の考える佐渡中等教育学校を含む高校のあり方とはどのようなものか
- 「新たな学校再編計画」策定の取り組み状況について
本計画は児童生徒数の減少を前提にあり方を検討するようだが、減少だけでなく、島外から児童生徒を受け入れる「離島留学」による児童生徒増加策の検討はしないのか
- 令和2年6月新潟県議会定例会での総務文教常任委員会において、令和5年度に佐渡中等教育学校の募集を停止し、佐渡高校と統合するとの再編計画が示された。その後、渡辺市長や県議会総務文教常任委員会などの取り組みにより、令和2年7月県立高校等再編整備計画では募集停止の記載が削除されたが、「佐渡中等教育学校のあり方について検討する」との事項が追加された
- 新型コロナウイルスの感染拡大による誤解や差別・偏見に対して、佐渡市として人権を守るメッセージや学校・職場への啓蒙活動などが必要であり、直ちに実施すべき
順位:4、 質問者:中村良夫
9月9日(水曜日)午後
- 新型コロナウイルス感染拡大防止対策について
- 現段階において感染拡大を防止するには、国による財政支援の拡充によりPCR検査を大規模に実施し、陽性者を隔離、保護する取り組みを行う以外に方法はない
- 医療機関、介護施設、福祉施設、保育園、幼稚園、小中学校、高校など、集団感染のリスクが高い施設に勤務する学校給食センターやスクールバス運転手などの職員及び出入りする業者に対して、定期的なPCR検査を行うこと。また、必要に応じて、施設利用者全員を対象にPCR検査を行うこと
- 検査によって明らかになった陽性者を隔離、保護、治療する体制を早急に作り上げること 以上のことを佐渡島内で早急に実施すべき
- ア.陽性者のうち、無症状患者、軽症患者への宿泊療養施設の確保
- ィ.自宅待機を余儀なくされる人への生活物資の届けと体調管理の体制
- ウ.中等症患者、重症患者を受け入れる病床の確保
- エ.新型コロナウイルスの影響による医療機関の減収に対する補償。また、医療従事者の処遇改善、危険手当の支給、心身ケアの思い切った財政支援
- 現段階において感染拡大を防止するには、国による財政支援の拡充によりPCR検査を大規模に実施し、陽性者を隔離、保護する取り組みを行う以外に方法はない
- 熱中症対策について
保育園、幼稚園、小中学校、高齢者のひとり暮らしなど - 柏崎刈羽原子力発電所について
- 2020年7月12日に地元新聞に掲載された地元同意の範囲についての首長の見方と理由などに対する佐渡市の見解
- 「3つの検証」なしに再稼働の議論なしについての見解
- 主要地方道佐渡一周線の松ケ崎地内と松ケ崎-岩首間の終日全面通行止めに対する佐渡地域振興局の対応について
- 本年7月15日と7月31日の対応について
- 保育園や学校、消防車や救急車などの緊急車両、地域住民への対応について
- 今後の主要地方道佐渡一周線の道路改良工事のスケジュールについて
順位:5、 質問者:中川健二
9月10日(木曜日)午前
- 佐渡航路の安定と充実
佐渡市としての航路のあり方を問う - 佐渡の文化遺産の保存を求める
佐渡の文化的財産の継承にもっと取り組むべき。また、唯一の佐渡植物園の利用率向上のための取り組みを望む - 廃屋の早急な対処を望む
金銀山を世界遺産として世界に発信する佐渡に廃屋が放置されている様は胸を張れるものではない。早急な対処を求める - 人・農地プランの実質化
人・農地プランがまだまだ進んでいない地域への推進を求める - 佐渡市が雇用している非正規職員の処遇改善を求める
佐渡市の正規職員の削減は表向きには経費削減に見えるが、その反面として官製ワーキングプアを生む結果となっているため、改善すべき - 庁舎建設問題
合併特例債など国の制度を利用して施設を便利なものにしたい気持ちは理解できる。しかしながら、人口を増やし住みやすい佐渡にするには、施設ではなくマンパワーが必要なのではないか
順位:6、 質問者:平田和太龍
9月10日(木曜日)午後
- 市長の所信表明について問う
- 佐渡の教育のあり方について
- 所信表明にキャリア教育や佐渡学のことしかないが、市長は教育の取り組みをどのように考えているか
- 教育行政方針にある不登校生徒の対応や適応指導教室、訪問指導員との連携について、今後の取り組みを具体的にどのように考えるか
- 学校現場において、先生と一人ひとりの児童・生徒と向き合える時間が必要だと思うが、市独自の政策はあるか
- 課題を抱えた子どもの保護者を支援するための取り組み状況はどうか
- 教育委員会において、子ども若者相談センターや関係機関との連携についての取り組み状況はどうか
- 学校教育現場において、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー、臨床心理士、保健師等専門員の拡充が必要と思うが、どのように考えているか
- 島留学について、市長は今後どのように取り組んでいくのか
- 小規模小・中学校において、事務職員の配置がなく、管理職が事務仕事も自身の職務と兼務しているが、職務軽減やミスチェックの観点から事務職員を配置すべきと考えるが、どうか
- 子育て支援について
- 所信表明にある屋内遊技場の確保についての現実的な取り組み状況
- 子どものスポーツや文化活動の支援をしたいとあるが、今後具体的な取り組みについて問う
- 佐渡の教育のあり方について
順位:7、 質問者:山本健二
9月10日(木曜日)午後
- 真野体育館、公民館は存続すべきではないか
- 高齢者や弱者の交通について問う
- 防災拠点庁舎整備について問う
順位:8、 質問者:北啓
9月10日(木曜日)午後
- 放置自動車について
放置自動車発生の防止及び処理に関する条例を制定すべき - スマホ決済アプリによる市税等の納付を実施すべき
- 地域通貨について
- 現在の利用者数、使える登録店舗数などの現状はどのようになっているか
- 地域通貨の目的と今後の戦略をどのように考えているか
- サービス拡充の提案
- 新型コロナウイルス対策について
- リフォーム補助の実施を
自宅でも「新しい生活様式」へ対応するため、リフォーム補助の実施をすべき - 移住促進事業を拡充し、実施すべき
- 奨学金助成制度を早期に実施すべき
- 医療従事者、保育士、介護士などの移住に対して補助を拡充し、PRを強めるべき
- テレワークでの転職しない移住に対し、補助を実施すべき
- 佐渡市独自の慰労金の支給を
保育士、児童クラブ勤務者などコロナ禍の中、保育サービスを継続していただいた方々に対し、慰労金を佐渡市独自で支給すべきと考えるが、どうか
- リフォーム補助の実施を
- 教員の働く環境整備について
- 公務支援システムの導入について
- 学校事務員の配置について
順位:9、 質問者:中川直美
9月11日(金曜日)午前
- 新型コロナウイルスに対する市民の暮らし支援について
インフルエンザ等の感染が増える冬の前に、新型コロナウイルス対応、支援のためのアンケート等を市民から徴取し、その内容に基づいて対応を考えるべきではないか - 合併特例債の活用、最上位計画の佐渡市総合計画について
- 合併特例債の活用について、前市政との違いは何か
- 防災拠点庁舎整備の市民説明会において、改修、建設必要なし等の反対意見の1つは分庁対応で可能というものであった。これは各地域の活性化の内容を含んでいるものであり、地域づくりと本庁と支所、行政サービスセンターのあり方が問われていると考えるが、どのように受け止め、対応していくか
- 総合計画の策定は、地域づくりの将来展望や各行政分野で市民との共有・協働を基に進めるべき。また、行政改革大綱(実施計画)は、時代に合ったものに変更すべき
- 佐渡航路問題について
- 両津〜新潟航路のジェットフォイルぎんがの更新、小木-直江津航路の高速カーフェリーあかねの売却等、航路問題が佐渡経済等に与える影響及び市の今後の姿勢
- 平成27年(2015年)時から、航路事業者における課題が明確になっていたにもかかわらず放置してきた佐渡航路確保維持改善協議会の責任は重いのではないか
- 航路や事業者のあり方に鑑みて、筆頭株主である新潟県は現在の38%の出資比率を本来の50%に戻す必要がある
- 水道水硬度の改善について
厚生労働省の「管理上留意すべき基準」、「おいしい水の水質要件」、「快適水質項目目標値」等は、水道水硬度は10〜100mg毎リットルとなっている。島内において、給水人口の3割がこの数値を超えており、ボイラー等の機器の痛みが激しく、改善を求める声がある。抜本的な改善はできないとしても、家庭用の硬度低下機器への補助制度を創設すべきではないか - 茅葺き能舞台の保存のあり方について
佐渡の歴史や文化を示す1つである各地に点在する能舞台は保存、継承すべきである。特に、茅葺き能舞台の維持は困難になっているのではないか。行政としての対応方針はどのようになっているか
順位:10、 質問者:上杉育子
9月11日(金曜日)午後
- 農業政策について
- 平成31年1月に策定された農業ビジョンに対する市長の見解を問う
- 地産地消の推進と生産量の確保対策について
- 園芸産地再生担い手育成事業の実証結果と今後について
- 園芸振興を図るには、生産者が安心して取り組めるような政策や支援策が必要と考えるが、市長の見解を問う
- 世界農業遺産(GIAHS)認定を受けた佐渡市として、トキ認証米制度の事例を他の農林水産品目にも波及させ、健康と環境と地域を守る食への取り組みを推進すべきと考えるが、市長の見解を問う
- 佐渡米品質向上プロジェクト事業について
- 子育て支援の1つに在宅育児に対する支援策が必要と考えるが、市長の見解を問う
- 金井地区における支所・行政サービスセンター機能について、市長の見解を問う
順位:11、 質問者:駒形信雄
9月11日(金曜日)午後
- 所信表明について
- 地域の特色に合わせた再生への取り組みには、どのようなものを考えているか
- 産業振興について、新たな制度創設の内容
- 農業政策について、モデル事業はどのような内容か
- 佐渡地域医療体制について、何が問題点と捉えているのか
- 農林水産業について
- 園芸作物を含めた今後の農業戦略について
- 販売網構築事業の見直しも含めた戦略をどのように考えるか
- 農業公社の方向性について
- 離島漁業再生支援事業について(ナマコ種苗生産の取り組み状況等)
- 新型コロナウイルス感染症に対する経済対策について
- 佐渡独自の支援策の利用状況
- 子育て支援策について、十分に告知されているのか
- 追加の支援策をどのように考えているか
- 雇用調整助成金の延長に伴う取り組みについて
- 観光戦略について
- 観光客が減少している中、DMOと連携した誘致対策
- 県の観光支援キャンペーンに対して、佐渡市の取り組み状況
- 滞在型観光促進事業の利用状況と今後の対策について
- 交流居住・定住促進事業の取り組み状況とさどまる倶楽部会員の状況
- 佐渡クリーン認証の効果について
- Go To キャンペーンの利用状況と今後の取り組みについて
- 奨学金貸与事業の3年間の利用状況について
- 佐渡汽船に対する交渉状況について
順位:12、 質問者:後藤勇典
9月11日(金曜日)午後
- 新型コロナウイルス対策について
- 現場サイドの情報を集める仕組みの構築について(議会特別委員会の設置要請、有識者定例会議の設置など)
- ベースとなる支援策は通期かつ次年度以降も実施すべき
- インフォデミック(噂・恐怖心の感染)にはどのように対応するか
- 秋冬に向けた医療物資の支援について
- 失業対策としての奨学金等活用策について
- 子育て支援について
- 保育園・幼稚園の受け入れ状況について
- 保育・幼児教育の無償化による本市の影響について
- 私立保育園の補助事業について
- 保育園・幼稚園・認定こども園における再編及び民営化等、市の基本的な考え方について
- 佐渡汽船について
佐渡汽船は、小木〜直江津航路において、ジェットフォイルをリースし、高速カーフェリーあかねの代替船として対応していくことを公表している。しかしながら、世界規模のコロナ禍においては、1年以内に船が売却できない可能性も十分に考えられる。また、想定を大きく下回る安値で取引されることにより、債務超過の解消に大きく寄与できない可能性も考えられる。そこで、高速カーフェリーあかねが売却できず、そのまま使い続けるパターンも考慮する必要があるものと考える。市はどのような対応策を考えているか - 防災拠点庁舎整備について
- 市民サービス向上のための複合庁舎整備(中央図書館等)について
- ゼロカーボンアイランドの実現を見据えた、将来ランニングコスト低減のための「省エネ庁舎(断熱性能・エネルギー効率)」の整備について
- 新保川の河床掘削について
- 職員数の見直し(会計年度任用職員等を含む)及び業務の効率化について
順位:13、 質問者:荒井眞理
9月14日(月曜日)午後
- 人が人らしく生きられる佐渡を実現するために
- 新型コロナウイルス感染を守りの体制強化でブロックし、不安のない自信を回復した自由な佐渡の生活を取り戻すことに全力をあげよ
- PCR検査体制を市独自の政策で充実させること
- PCR検査センターを県とは別に民間事業者へ委託し、佐渡市の検査体制の幅を広げること
- 島の入り口となる新潟港、直江津港で他からの入島者への検査の義務付けを行うこと
- イベントや会議など関係者を島外から招くことがあらかじめ分かっている場合には来島者へのPCR検査を義務付けるべき
- 医療機関、福祉施設、幼稚園・保育園、学校など社会機能を保つために必要な機関のエッセンシャル・ワーカーに対して、無料で定期的にPCR検査を実施すること
- 島民が消費しやすい環境の回復を徹底的に推進し、生活に必要なあらゆる分野での島内経済を活性化させること
- 新型コロナウイルスの特徴を市民に積極的に知らせ、意味のある対策に努力し、無意味な対策に疲れないようにすべき
- 公共施設を利用した市民の個人情報を集めているが、主催者への協力義務とし、情報管理についても一定のルールを作るべき
- PCR検査体制を市独自の政策で充実させること
- 子どもの人権を守る佐渡の実現を図るべき
- 子ども同士のいじめ、大人からの虐待をゼロにすることの大切さを大人が学ぶ機会を作るべき
- オンライン授業のための整備として進めているICT環境のメリット、デメリットを子どもたち自身に正しく伝えるべき
- コロナ禍の3密を避けるため、1クラス25人学級を実現させるべき
- これらの学校教育の環境を整備するために教職員数を増やすべき
- 障がい福祉政策の停滞を打開せよ
- 障がい者の就労先数に限度が見え始めている。社会の大切な人材であることを踏まえ、仕事の開発、創設に積極的に取り組むべき
- 家族会の規模縮小化の傾向があるが、家族会の活動を佐渡市はもっと重視し、協働すべきである
- 市の計画策定について、条例化する必要があるのではないか
- 前市長の目指した佐渡市将来ビジョンを止め、佐渡市総合計画を策定するとのことだが、どの計画がどの位置付けなのかを条例化により市民に解りやすくすべき
- 最上位計画がありながら「新たな学校再編計画」策定などが同時進行するのはおかしい。このようなことを解消すべきである
- 庁舎建設の議論の仕方について、反省点が多く残ると思われる。後世に残る議論とそれらの記録を残すべきである
- 市の予算から無駄な支出をなくすため、徹底的に分析、評価すべきである
例えば、除雪事業予算は歴代市長によって変わることがおかしいと指摘してきた。メスを入れにくい分野も含め、丁寧な見直しを求める - 博物館ビジョンの策定は遅れているが、どうなったのか。博物館の価値を高めるため、議論をきちんと進めるべき
- マイマイガの大量発生、連日の大雨、その後の連日の猛暑と、気候変動の危機に結び付いていると考えられる問題を解決するために、海で囲まれた島である佐渡は積極的に取り組むべきである
- 佐渡市はハラスメント防止対策が非常に弱い。それに対して、どのようにするつもりなのか
- 新型コロナウイルス感染を守りの体制強化でブロックし、不安のない自信を回復した自由な佐渡の生活を取り戻すことに全力をあげよ
順位:14、 質問者:稲辺茂樹
9月14日(月曜日)午前
- 市長の政治姿勢について
- 庁舎整備の今までの流れについて
- 新型コロナウイルス感染対策について
- 観光施策について
- 佐渡汽船について
順位:15、 質問者:近藤和義
9月14日(月曜日)午前
- 北方領土問題に対する市長見解
- 核兵器禁止条約に対する非核平和宣言都市の市長見解
- 出産祝金制度の来年度実施に向けての進捗状況
- 庁舎建設の内容と今後のスケジュール
- 会計年度任用職員の賃金・労働条件は、国のマニュアルを踏まえ、同一労働・同一賃金の観点から正規職員との均衡を図るべきではないか
- 農業政策
- 令和2年産米のJA仮渡金の大幅減額に対する市の対応
- 農耕用大型特殊自動車とけん引の免許取得に対して、市の支援が必要ではないか
- 格安航空会社(LCC)新設構想の進捗状況
- 特定空家に対する市の対応
- さくらねこ無料不妊手術事業の現状と計画
- 新型コロナウイルスの感染防止と経済対策の本市の取り組み状況