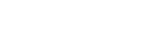本文
市長公務日誌(令和7年5月)
佐渡市民生委員児童委員協議会
令和7年5月28日 水曜日
「佐渡市民生委員児童委員協議会」は、佐渡市内における民生委員児童員の資質の向上、相互の連携及び地域活動の充実強化を図り、地域社会における福祉事業の推進に貢献することを目的としています。現在、209名の方が各地域で身近な相談・支援者としてご活躍頂いております。
民生委員のなり手不足が全国的な課題となっていますが、佐渡市として、今後も引き続き、民生委員の制度や活動を正しく理解していただき、民生委員にとって活動しやすい環境整備を進めてまいります。
野生生物保護功労者表彰 文部科学大臣賞受賞の報告を受けました
令和7年5月27日 火曜日
佐渡市立行谷小学校が、令和7年度野生動物保護功労者表彰で文部科学大臣賞を受賞されました!とても嬉しいニュースです。
行谷小学校は、全校でトキの保護活動や「トキ学習」を行い、地域の方々と協力してトキのえさ場環境整備や水辺の生きもの調査等を実施してこられました。また、中国や韓国の子どもたちとも交流し、「トキ解説員」を披露するなど、日本と中国の友好交流に貢献されたことが評価されました。
道の駅あがの佐渡フェア

令和7年5月25日 日曜日
道の駅あがので佐渡フェアが開催されました!
佐渡市は県内各自治体と広域的に連携し、新潟県の魅力発信や観光誘客等に取り組んでいます。多くの方に佐渡の魅力を知っていただけるよう今後も引き続き、取り組んでまいります。
佐渡南ロータリークラブ創立50周年記念式典
令和7年5月24日 土曜日
佐渡南ロータリークラブが創立50周年を迎えられました。誠におめでとうございます。
一昨年、佐渡南ロータリークラブ創立50周年記念事業の一環として、佐渡市役所新庁舎の正面に宮田亮平様の揮毫(きごう)による「佐渡市役所」の銘を刻んだ「神子岩」を設置いただきました。「神子岩」は、太古の火山活動により、幾千もの隆起や浸食を繰り 返して形成された佐渡島の成り立ちを物語るものであり、佐渡市名誉市民である宮田亮平様の文字が刻まれたことで、歴史的・文化的な価値を添えた佐渡市の新たなシンボルをいただくことができたと嬉しく思っています。
佐渡金銀山世界遺産登録推進県民会議解散式及び「佐渡島の金山」保存活用推進ネットワーク発足式

令和7年5月22日 木曜日
令和6年7月に「佐渡島の金山」が世界文化遺産に登録されたことを踏まえ、県民会議を解散し、新たな団体である「佐渡島の金山」保存活用推進ネットワークが発足しました。
これまでの間、先人たちが守り育ててきた佐渡の宝に、世界遺産という新たな光があたり、今後の保存管理に対する責務について身が引き締まる思いです。これまでの活動や想いが新たな組織に引き継がれ、「佐渡島の金山」を次世代に継承するための大きな原動力になることを大いに期待しております。
自民党「有人国境離島地域の保全・振興を推進する議員連盟」及び公明党離島対策本部会議


令和7年5月21日 水曜日
自民党「有人国境離島地域の保全・振興を推進する議員連盟」において、有人国境離島法に係る佐渡市での取組をご説明するとともに、公明党離島対策本部会議にて、佐渡市の課題・対策・要望等について各省庁と意見交換を実施しました。要望の多くはライフラインの維持であり、離島ならではの課題について切実にお伝えしました。
今後も引き続き、佐渡市長そして全国離島振興協議会副会長としても離島の市長村長とともに要望活動等に全力を尽くしてまいります。
有人国境離島法とは・・・国境に接する離島に人が継続して居住できるよう、国が積極的に関与し、領海や排他的経済水域を保全することを目的とした特別措置法で、2027年3月末に有効期間が満了する
2025佐渡ロングライド210

令和7年5月18日 日曜日
2025佐渡ロングライド210、大きな事故もなく無事に開催することができました!大会開催にあたりご協力いただいたスタッフとボランティアの皆さま、関係者の皆さま、沿道で応援してくださった市民の皆さまに心より感謝を申し上げます。
今年は210kmに初エントリーしました!当日は風が強く、苦戦を強いられましたが、無事に完走することができました。
自然と近い距離で楽しむことができる自転車の魅力を再発見するとともに、改めて佐渡の美しさを実感しました。参加者の皆さんとも会話しながら、また、楽しそうな様子を間近で見ることができて、大変充実した時間を過ごすことができました。
佐渡市健康推進協議会総会
令和7年5月14日 水曜日
佐渡市健康推進協議会は、「市民の健康増進に関する意識の高揚を図り、健康で豊かな地域づくりに貢献すること」を目的とする市民団体です。健康推進委員の皆さまは、自分が元気になること、そして家族や地域へ元気のおすそ分けをしていただき、子どもから大人まで各世代に応じた市民協働の健康づくりのため、日々取り組んでいただいております。改めて心より御礼申し上げます。
生涯を通じて健全な生活を実現するためには、関係者の皆さまとの連携はもちろん、人との繋がりを大切にした健康づくりが大切だと考えております。今後も引き続き、総合的な健康づくりに取り組むとともに、健康推進委員の皆さまには、地域の健康づくりリーダーとして、益々活躍していただきたいと思います。
台湾の高雄市立龍華小学校の皆さんが来島されました
令和7年5月14日 水曜日
台湾の高雄市立龍華小学校の皆さんが市内の小学校との交流を深めるため、来島されました。
台湾高雄市との交流は、佐渡市出身の著名な政治家である「山本悌二郎」氏が台湾製糖株式会社の創設に関与され、数々の重職を歴任されたことから始まっております。そして、令和5年度には友好交流都市を結び、相互の交流を益々深め、観光のみならず文化の交流も深めていこうと考えております。
高雄市立龍華小学校の皆さんにとって佐渡を来島したことが、かけがえのない思い出となることを心から願っております。
ジェローム・ライアン一等書記官が視察にお見えになりました
令和7年5月13日 火曜日
在日米国大使館のジェローム・ライアン一等書記官が、曽我さん母娘の拉致現場等を視察するために来島されました。佐渡市の拉致の現状や取組の経緯等を説明し、拉致現場も視察していただきました。ジェローム・ライアン一等書記官からは、「拉致被害者が一日も早く帰国できるよう日本政府の取組を支持する」との心強いお言葉をいただくことができました。
今後も引き続き、関係3市で拉致問題の早期解決に向け、取り組んでまいります。
寄附金贈呈式

令和7年5月12日 月曜日
新潟縣信用組合様から、佐渡市世界遺産推進基金へ多額のご寄附をいただきました。毎年、世界遺産基金への寄附をいただいております。心より御礼申し上げます。世界に認められた「佐渡島の金山」の魅力を多くの方々に知っていただけるよう、今後ともご尽力賜りたく存じます。
棚田みらい応援団田植え

令和7年5月11日 日曜日
新潟県では、SDGsの取組みやボランティア活動などの一環として、棚田保全活動に参加していただける企業「棚田みらい応援団」を募集しており、今回、「棚田みらい応援団」と歌見地区で田植えを行いました。民話「鬼の田植え」になぞらえて、鬼の衣装を身にまとっての田植えでした。
今年はあいにくの空模様でしたが、地元の集落の皆さまや企業の皆さまと一緒に「田植え」という作業を通じ、触れ合うことができたことは、大変貴重な機会であったと感じております。棚田保全に向けた取組みに限らず、様々な場面でこのご縁が人と人を結んでくれることを大いに期待しております。
金塊づかみセット寄贈式

令和7年5月9日 金曜日
新潟県全体の活性化やインバウンド拡大を目指し、県内各市と様々な連携に取り組んでいます。令和6年10月には新潟県が誇る「泳ぐ宝石」と称される小千谷市の「錦鯉」を寄贈いただき、今回は佐渡市の「佐渡島の金山」の世界遺産登録を踏まえ、金塊掴みセットを寄贈させていただきました。
今後も引き続き、小千谷市との連携に取り組んでまいります。
台湾の南投県私立五育高校の皆さんが来島されました

令和7年5月6日 火曜日
台湾南投県の私立五育高校の皆さんが来島されました。日帰りの弾丸ツアーでしたが、佐渡の魅力をたくさん感じていただけたと思います。佐渡に来島されたことが、かけがえのない思い出となることを心から願っております。
佐渡市野球リーグ戦大会
令和7年5月4日 日曜日
今年も佐渡市野球リーグ戦大会が始まりました!今年はあいにくの曇り空でしたが、野球選手の皆さんと交流しながらの始球式は楽しい時間を過ごすことができました。野球に限らず、様々なスポーツの参加により、心身ともに健康の保持と増進に取り組んでもらえると嬉しいです。
今年のロングライドは210kmに挑みます!怪我をしないよう早朝のトレーニングでしっかり体を作っていきたいと思います。